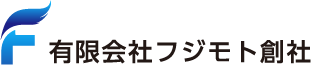自宅の外壁に藻·カビ·苔が発生していませんか?
新築して間もないのに?
再塗装して間もないのに?
ここでは、外壁モルタル壁·サイディング壁になぜカビ·藻·苔が発生するのか?
そしてその対処法と、どんな塗料で塗装するとカビ·藻·苔が生えにくいかについてご説明します。
まず、カビ·藻·苔について当社に寄せられた、お客様の疑問にお答えする形で見ていきましょう。
①そもそも外壁になぜカビ・藻・苔が発生するの?
住宅外壁をよくみると、外壁の一部や北側の外壁などに黒色や緑色に変色している現象が多く見うけられます。
これらの多くは、大気環境下で生息する藻類や真菌類などの微生物が外壁に付着して生育しているものです。
建築後、早いものでは1年以内に、遅いものでも数年後には外壁表面に藻類の付着·生育が見られるようになります。また、藻類が生育している部分の多くは水分の流下·停留しやすい場所であり、材料表面の劣化が発生しやすい場所です。
それでは、どんな場所に発生しやすいのでしょうか?
①地域差…日本各地ほぼ検出される
②日当たり及び湿潤程度…カビ類と藻類は日当たりが悪く湿潤状態で発生し、汚染の主な 原因になっています。蘚苔類は比較的日当たりが良く湿潤な状態が保たれている場所に多い。
③周囲環境……どの地域でも、樹木が近接している部分が汚染が多くみられ、住宅の壁面が高含水状態が保たれている場所に多い。 苔類は他の微生物に比べ地表面に近い位置(地上高30㎝まで)に限られている。 カビ類は他の微生物と共存していない場合があります。
以上のことから、住宅の壁面に多発生しているのは藻類·カビ類がほとんどで、屋根などの水平面には苔の発生も見受けられます。
②カビ・藻・苔の違いって何?
カビ・・・真菌類(しんきんるい)と呼ばれ,菌糸と呼ばれる糸状の細胞からなり、胞子に よって増殖します。 光合成をしないので何らかの栄養素が必要で日の当たらない湿った場所に発生します。
藻類・・・光合成を行う生物のうち、コケ植物・シダ植物・種子植物を除いた残りすべての生物のことです。 多くの藻類は、海水・淡水中に生育しますが生育の場所は多様です。 藻類の内、住宅などに発生するものは気生藻類とよばれています。
苔……蘚苔類(せんたいるい)と呼ばれ、道路の端や日陰の湿った所ではよく見られ、コケの仲間をまとめてコケ植物と言います。 一般的な植物は地面から吸収した水分を葉まで届けるために維管束という管が発達していますが、この蘚苔類には維管束がハッキリしていません。 体を固定する根のような部分があり、水分吸収が出来、わずかな光合成を行います。
ざっくり言うと苔と藻類は光合成を行う植物、カビは光合成を行わない菌類です。
③新築して間もないのになぜカビ・藻・苔が生えるの?
新築して間もないモルタル外壁やサイディング造り住宅の壁や、再塗装して間もない外壁にカビや藻が発生しているのをよく見ます。
近くに水路があったり、樹木が近接しているなどのカビ·藻が発生しやすい周辺環境のほかに、サイディング壁の場合は、サイディングの模様に問題があるにではないかと思われます。 (ここからは、当社のの考察です)サイディング壁に藻が発生している現場をよく見てみると、決まって細かな模様が水平方向に入っているサイディングにこの現象が多く見うけられます。また、モルタル外壁の場合は、砂状の塗料材(リシン·弾性リシン·スキン等)の材料に多く見受けられます。
これは明らかに塗装時の使用材料や模様が影響していると思われます。
上記2つの共通点はゴミがたまりやすく、水分が滞留しやすい構造になっていると言うことです。
これらのことは、同じ時期に建築され隣接したサイディング壁の住宅外壁面で水分が滞留しやすい模様かそうでないかによって明らかに藻の発生の違いが見られる事
そして、そのカビ·藻が発生しているサイディング壁でも直接雨がかからない上部壁面·ヒサシの下などで藻の発生が明きらかに少ないからです。
④我が家の外壁に発生しているのは、カビそれとも藻?
壁に発生しているのはカビでしょうか、それとも藻?それともコケ? まず第一に、カビ·藻·苔の違いで記載したように苔は地表面に近い位置(地上高30㎝まで)に限られることから除外して良いでしょう。 それでは、カビか藻か? 藻は光合成をしますのでわずかでも光と水分が必要です。カビは光合成をしませんので栄養源でもある、ホコリ・ゴミなどと水分が必要です。 これらのことから日光が少しでも当たる部分は藻。日光が全く当たらない部分はカビの可能性が高いと言えます。 また、カビと藻は生態が非常に近い関係にあります。 藻は気温が25℃を超えると死滅していきますので、その死滅した藻を栄養素にカビが生えるなどしているものと思われます。
いずれにしても建物にも健康にも良くありませんので、早めに取り除いた方が良いでしょう。
⑤カビ・ 藻・苔の影響 健康面に問題があるの?
藻やカビは表面で繁殖するだけで根を建物の内部まで伸ばすわけではありませんので、建物の構造体に対して特に悪影響を及ぼすまでにはなりません。
藻類とカビなどの真菌類は非常に近い仲間で、その生態もよく似ています。 そのため藻類が生育しやすい部分はカビなどの真菌類も生育しやすいといえます。
このカビ類の中には健康に大きな被害を及ぼすものも存在し、経口吸入·経皮などで体内に入り健康障害が発生したりするものも存在します。
いずれにしても 藻やカビが発生する場所は水分が滞留しやすく、藻類自体保水性がありますので材料の劣化も発生しやすくなることから、早めに処理しましょう。
⑥カビ・藻等が発生した場合のメンテナンスの仕方は?
①外壁表面にカビ・藻が見うけられたら柔らか布でこすり取る。
②中性洗剤を少し薄めて柔らかい布かブラシで水洗いする。
③高圧洗浄で洗い落とす。
高圧洗浄するときサイディング板の場合サイディング自体を劣化させてしまう恐れが
ありますので注意が必要です。
藻やカビを殺す薬剤を用いれば、繁殖を止めることが出来ますが、跡が残ることがあります。
漂白作用がある薬剤を使用すればカビに跡も残りにくいのですが、塗装膜自体を傷めてしまう恐れがありますので注意が必要です。
カビ·藻·苔に対する当社の取り組み
ここからは、当社のカビ·藻類に対しての取り組をご紹介します。
①築年数が新しい住宅の場合
建物が建築されて、2,3年しか経っていない住宅の場合それほどひどくない場合、基材を傷めない程度の水圧で高圧洗浄をする。 カビ·藻がひどく発生している場合、日本窯業外壁材協会が推薦する《ワンステップ·スプレークリーナー》をローラー又は噴霧器で処理します。
《ワンステップ·スプレークリーナー》とは

ニュージーランドのサーティーセカンズ社(30 Seconds Limited:本社オークランド市郊外》が開発した、その社名”30秒”にたとえられるほど極めて短い時間で抜群の効果を発揮するアウトドアー用のクリーナーです。 屋外の建造物の美観を損なわせるカビ·コケ、その他の汚れや黒ずみなどの除去の効果絶大な屋外用クリーナーで、ニュージーランドにおけるその知名度は抜群!市場占有率も80%を超えています。
■商品特徴■
屋外のカビ·コケ·地衣植物(菌類と藻類の共生体で固く除去し難い)、藍藻類の除去及び発生防止のために特別に開発した、効果抜群の屋外用クリーナーです。 効果は遅効性ですが散布後はそのままほうちしておくだけ(水洗いは不要)です。
噴霧後2~4週間(場合によっては数ヶ月)かけて徐々に枯れながら完全に死滅(除去)していきます。 また、散布後に製剤が表面に染み込み残るので、防カビ·防コケ(再発抑制)効果もあります。アルキル·ジメチル·ベンジル·アンモニウム·クロライド(別名:塩化ベンザルコニウム塩)を主成分(標準液:2%濃度、濃縮液9.9%濃度)とし、その他数種類の成分を独特な配合で取り入れたクリーナーですので、塩素系の洗剤が使用できない所にも使用できます。
■使用できないもの■
金属製品、合成樹脂製品などはシミやサビの原因となることがあるので使用できません。
■住宅建材への適応性の安全性■
代表的な建材(各種外壁材、タイル、レンガ、木材等)に直接散布しても影響がなく安全であることを確認しています。
引用元:アルタン(株)
②築年数が5年以上及び再塗装から5年以上の住宅
·それほどひどく発生していない場合は、機材を傷めない程度の水圧で高圧洗浄をし、防藻·防カビ性能が優れた塗料での再塗装を検討する。
·カビや藻がひどく発生している場合は、あらかじめワンステップ·スプレークリーナーでカビや藻を除去し、その後、機材を傷めない程度の水圧で高圧洗浄をし、防藻·防カビ性能が優れた塗料で再塗装を検討する。
*樹木が近接している場所や水路の近くなどの地域性により、カビや藻が発生しやすい場所は再発する危険性が高いので、確実に発生原因を見極めて除去処理を行う必要があります。 さらに、水分の滞留がある場所は出来るだけその原因を取り除いた上で、防藻・防カビ機能が優れた塗料で塗装する必要があります。
当社では、まず、お客さまの建物にどんな理由で藻·カビが発生しているのかを調査し、原因を特定した上で、お客さまの建物の構造·立地条件に合った防藻·防カビ効果が最大限発揮できる、最適な防藻·防カビ塗料を選択ご提案いたします。